

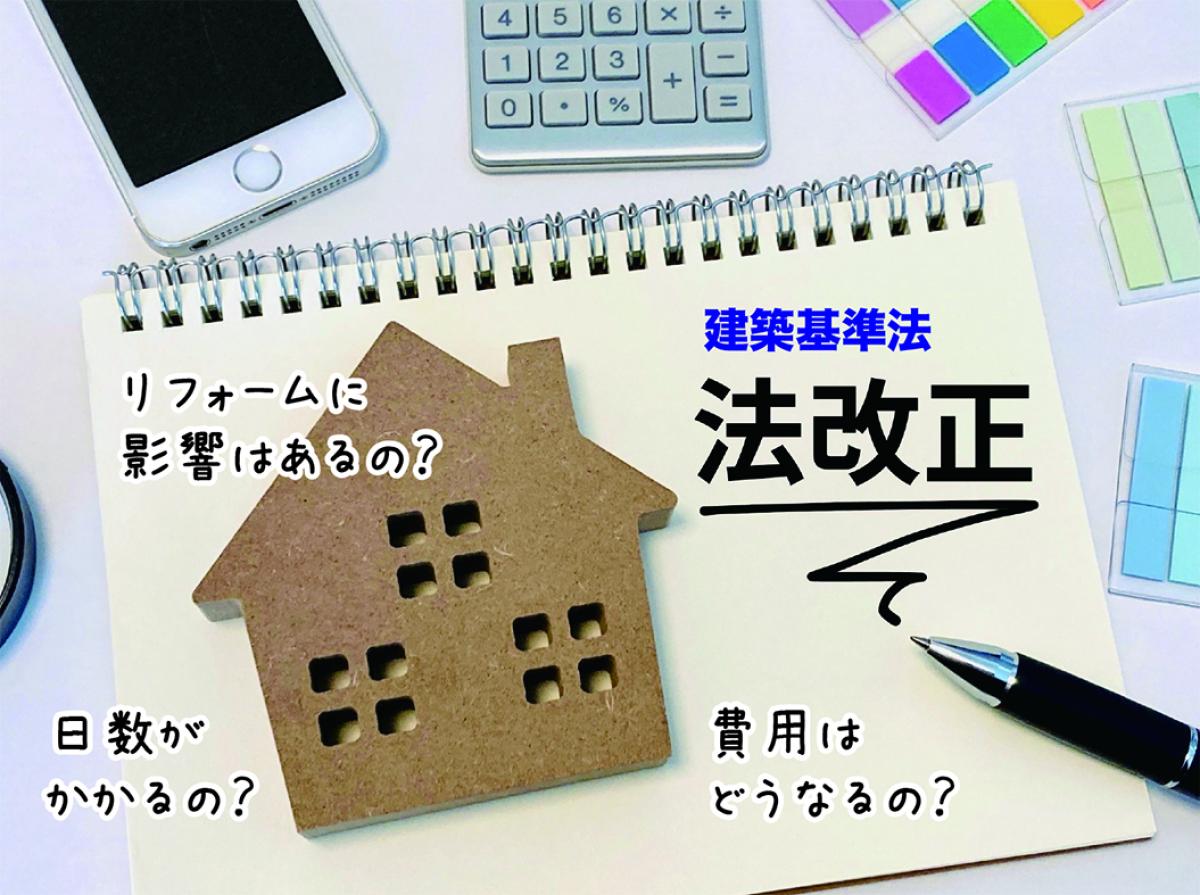
「2025年4月からリフォームのルールが変わる」と耳にして、少し不安になっていませんか?まもなく、建築基準法の改正により、リフォーム計画に大きな影響が出る可能性があります。しかし、どのような影響があるのか、具体的に理解できている方は少ないのではないでしょうか。2025年4月からの改正では、リフォームの一部に新しいルールが適用されるため、これまでよりも手続きや費用が変わるケースがあります。特に、どのリフォームが対象となるのか、自分が計画しているリフォームは影響を受けるのか、そして改正によって費用がどのように変わるのか、事前に把握しておくことが大切です。特に、どのリフォームが対象となるのか、自分が計画しているリフォームが影響を受けるのか、そして改正によって費用がどのように変わるのかといった点は、多くの方が気になるポイントでしょう。今回の記事では、法改正のポイントをわかりやすく解説し、焦らずに賢くリフォームを進めるためのコツをご紹介します。これからリフォームを検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
今回の建築基準法改正の大きなテーマは、「省エネの推進」と「木材利用の促進」です。その中でもリフォームに関わる変更として特に注目されているのが、「4号特例」の見直しです。
では、4号特例とはどういうものなのでしょうか?
4号特例とは、木造2階建て以下の住宅を対象にした特別なルールで、大規模な修繕や模様替えを行う場合でも、通常必要とされる建築確認申請を省略できる制度のことです。つまり、工事を始める前に役所や審査機関に提出する手続きをしなくてもリフォームができたため、手続きが簡単で費用や時間も抑えられました。これにより、一般の住宅リフォームは比較的スムーズに行うことができました。しかし、2025年4月以降はこの特例が縮小され、延べ床面積200㎡を超える木造2階建てや平屋(これを「新2号建築物」と呼びます)では、リフォームでも建築確認申請が必要になります。つまり、今後は家の骨組みを大きく変えるような大規模リフォームを行う場合、工事の計画を役所や審査機関に提出し、許可を得る必要があります。これにより、リフォームの手続きがより厳格になる一方で、住宅の安全性や省エネ性能が確保されるというメリットもあります。ただし、延べ床面積が200㎡以下の平屋(新3号建築物)については、これまでと同じく建築確認申請は不要です。
🔍 ポイント: この改正により影響を受けるのは主に「200㎡を超える住宅」のリフォームであり、一般的な住宅や小規模な改修には大きな変更はありません。

建築確認申請とは、建物の工事が法律に合っているかを確認するために、工事を始める前に役所や専門の審査機関に提出する手続きのことです。この申請を通じて、建物が耐震性や安全性、省エネ基準などの法律を守っているかをチェックします。リフォームの場合、特に家の骨組みや構造を大きく変更するような工事では、建築確認申請が必要になります。具体的には、工事の計画を示す図面や書類を提出し、審査が通れば「確認済証」が発行されて着工できます。建物の安全性を保つために大切な申請ではありますが、申請には時間と費用がかかります。
🔍 ポイント: 建築確認申請は、住まいの安全性や快適性を守るために必要な手続きであり、大規模なリフォームでは不可欠です。
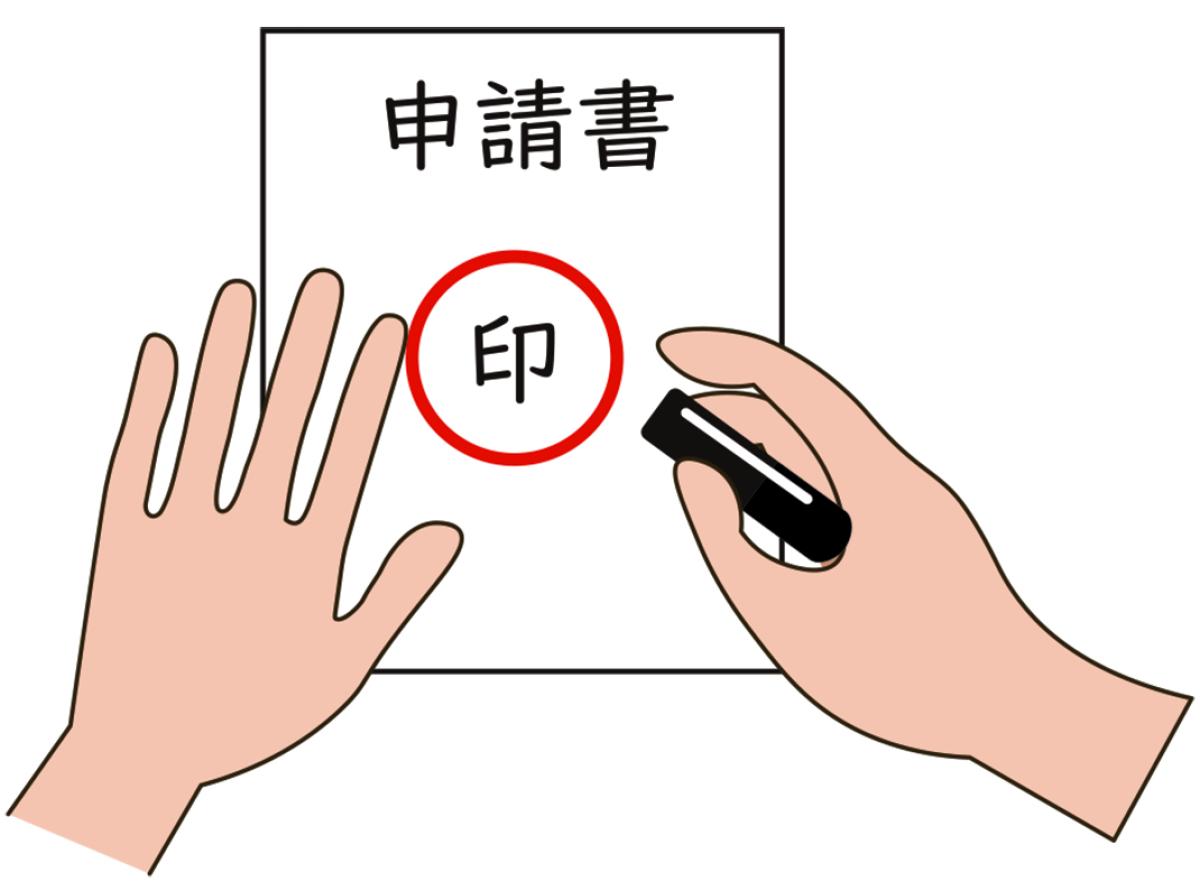
では、具体的にどんなリフォームで申請が必要になるのでしょうか?
【申請が必要なケース】
・屋根の葺き替え(下地交換を伴う場合)
・外壁の全面改修(外壁全体を新しくする場合)
・家全体の間取り変更やスケルトンリフォーム
・部屋の増築(防火地域では面積に関わらず、それ以外では10㎡を超える場合)
【申請が不要なケース】
・キッチンやお風呂、トイレの交換
・壁紙の張り替えや床の貼り替え
・外壁の塗り替えやカバー工法による改修
・屋根材や防水シートのみの交換
これらを見てもわかるように、大掛かりなリフォーム以外は、これまで通り申請不要です。特に水廻りのリフォームなどは今までと同じです。
🔍 ポイント: 建築確認申請が必要かどうかは「家の骨組み(主要構造部)」にどこまで手を加えるかによって決まります。

建築確認申請が必要になる工事をすると、以下のようなことが考えられます。
・費用が増える
・スケジュールが延びる
・既存不適格建築物の場合は追加工事が必要に
1つずつ見ていきましょう。
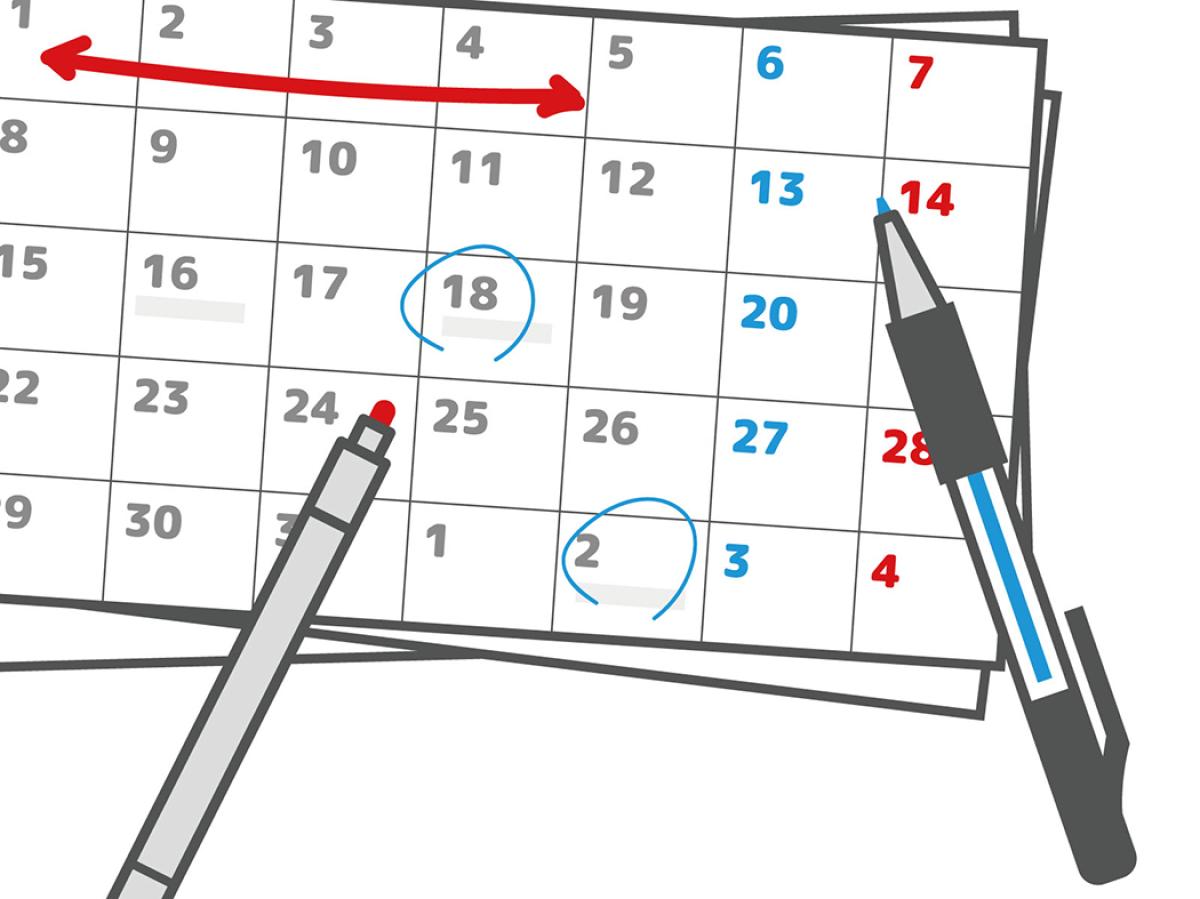
建築確認申請は建築基準法において、原則として建物の所有者やリフォームを依頼する人が申請を行うことになっていますが、申請には専門的な知識が必要です。そのため、専門家に代行を依頼するのが一般的です。ただし、この代行費用には通常、図面の作成や各種計算書の作成費用は含まれていないため、これらの作業が必要な場合は追加で費用がかかります。さらに、申請に伴う追加書類の準備や修正が必要になることもあり、その分の費用も予算に含めておく必要があります。これらのコストを事前に把握しておくことで、予算オーバーを防ぎ、計画的にリフォームを進めることができます。
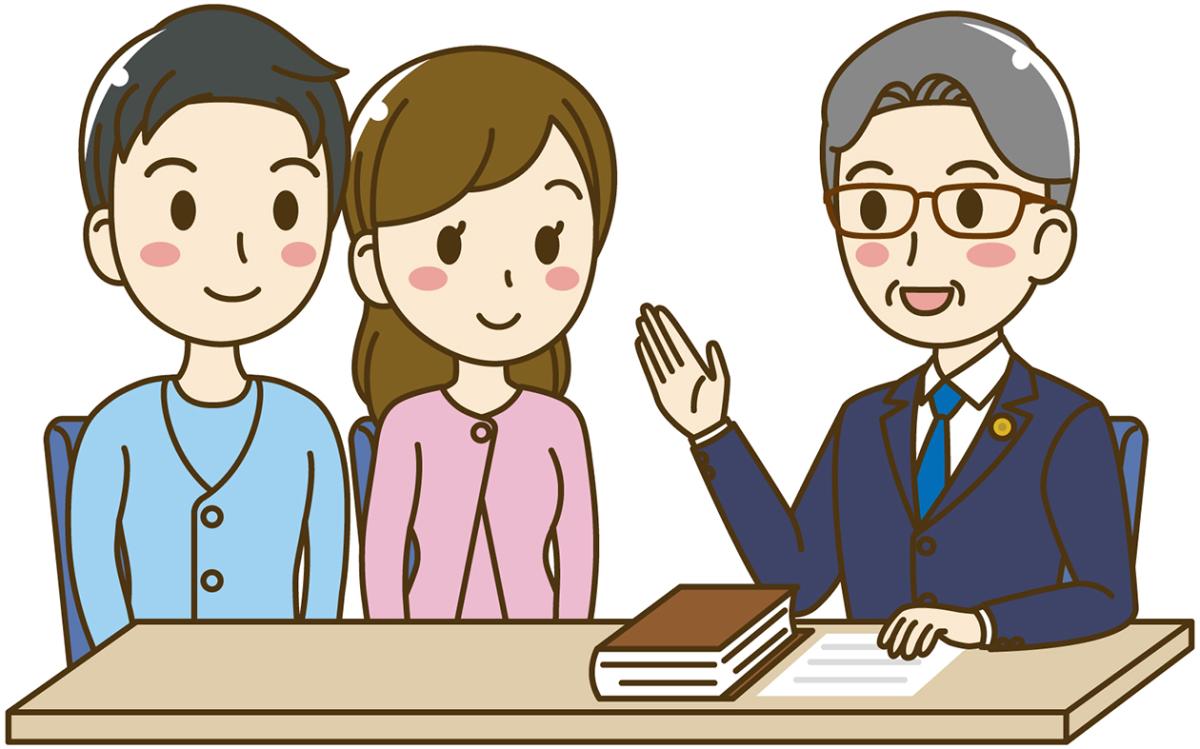
建築確認申請では、申請書類の作成から審査、許可が下りるまでに一定の期間が必要です。書類作成には建築士による図面や構造計算書、省エネ関連の図書などの準備が必要で、これに通常2週間から1ヶ月ほどかかります。さらに、役所や民間の審査機関による審査には1〜2週間程度を見込む必要があります。審査中に修正や追加書類を求められることもあり、その場合はさらに時間がかかります。結果として、着工までに通常よりも約1.5ヶ月から2ヶ月ほどの余裕を持つ必要があります。これを考慮して、リフォーム計画は早めに立てておくことが重要です。

築年数が古い住宅は、建築基準法が改正されるたびに適応外となる部分が増えるため、リフォーム時にはこれを最新の法律に適合させるための補強工事が必要になることがあります。例えば、耐震性の不足による補強工事、断熱性能の向上に向けた断熱材の追加、火災対策としての防火仕様への変更などが挙げられます。これらの工事は建物全体に及ぶため、費用も高額になる場合があります。特に、基礎部分や柱・梁の補強は大規模な工事となり、予想以上の費用がかかることもあります。そのため、既存不適格建築物のリフォームを検討する場合は、事前に専門家による診断を受け、必要な工事内容と費用を確認しておくことが大切です。

「2025年3月までにリフォームしないと!」と焦る必要はありません。改正後も小規模なリフォームはそのまま進められますし、大規模なリフォームでも計画をしっかり立てれば問題ありません。急いでリフォームをするよりも、まず早めに専門業者に相談し、必要な手続きや費用を把握しておくことが大切です。申請が必要な場合でも、早期の相談によって無駄な時間やコストを削減できます。また、着工までに通常よりも時間がかかるため、スケジュールに余裕を持つことが重要です。特に引っ越しや入居時期が決まっている場合は、早めに計画を立てることでトラブルを回避できます。さらに、信頼できるリフォーム会社を選ぶことで、法改正後の手続きや構造変更にもスムーズに対応できます。こういう時こそ、悪質な業者に騙されないよう信頼できる会社に頼むようにしましょう。
🔍 ポイント: 焦らずに正しい情報をもとにしっかりと計画的に進めることで、スムーズに進みます。
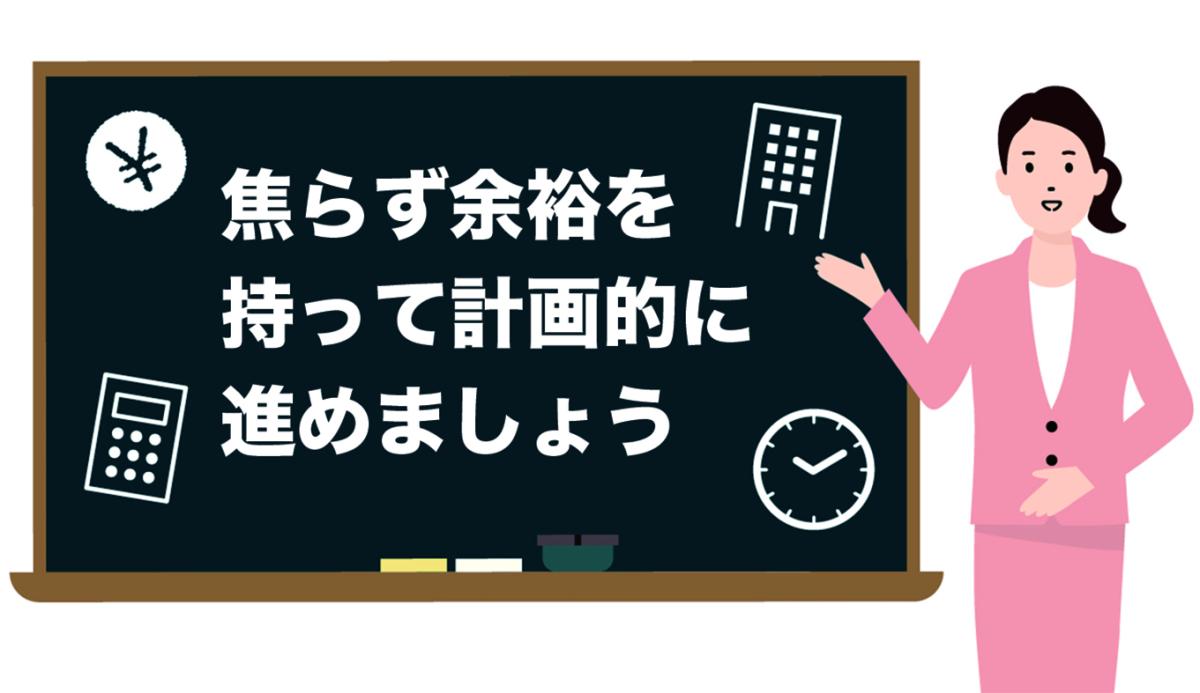
2025年4月の建築基準法改正は、一部の大規模リフォームに影響がありますが、すべてのリフォームが急がなければならないわけではありません。小規模な工事や200㎡以下の平屋は、これまでと変わらずに進められます。大切なのは、法改正を正しく理解し、計画的にリフォームを進めることです。焦って判断せず、家族や信頼できるリフォーム会社に相談しながらリフォームを考えていきましょう。
🔍 ポイント: 焦らなくても大丈夫。信頼できるリフォーム会社に相談するのが一番の近道です。

私たちヤマコーでは大工を経験し、その後、現場監督・設計デザインに携わっているスタッフが在籍しております。
そのため「家の造り方」を知り尽くしており、お客様の大切な家の長期的なアフターフォローも含めて、家をトータルでサポートするサービスを提供しております。
私たちヤマコーは、その場のリフォームに満足していただくだけではなく、安心してお住まいになるために長期的なサポートをしております。
大切な家のリフォームを安心して任せられる会社であるために3つの大切にしていること
・その場限りのリフォームを提案しないこと
・ご要望とご予算のバランスを考えた最適な提案をすること
・施工クオリティは地域NO.1であること
より良い家の状態を保つためには、数年後、数十年後を見据えた提案が必須です。
その場限りのリフォームでは安心してお住まいになることはできません。
言い換えれば、ご心配されていることは今すぐ必要な工事ではないかもしれません。
私たちヤマコーはお客様目線を追求し、「安心できる住まい」を軸に、家の状態とご要望、そしてご予算において最適な提案をいたします。
信頼関係をもとに、ご納得のプランニング、高い施工クオリティ、アフターフォローでお客様に満足を超えた感動を保証いたします。
リフォームをお考えの際には是非一度ヤマコーへご相談ください。
ご連絡先
0120-156-805
お問い合わせフォーム